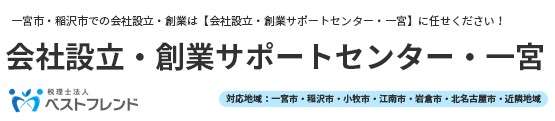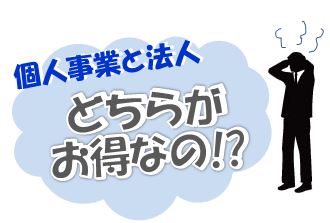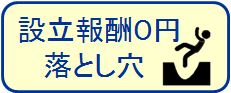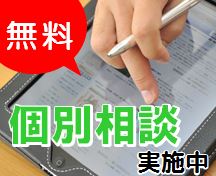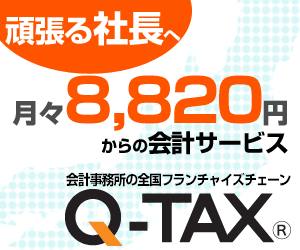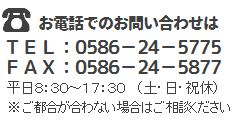�n�ƗZ��
�Z�����x�̎��
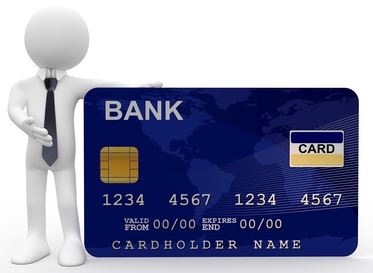 ������Ƃ̌���ł́A�u�Z���v�ƈꌾ�Ɍ����Ă����̎�������̋敪�ő傫��3�ɕ������l����K�v������܂��B
������Ƃ̌���ł́A�u�Z���v�ƈꌾ�Ɍ����Ă����̎�������̋敪�ő傫��3�ɕ������l����K�v������܂��B
�@ ���{������Z����
�A �ۏ؋���o�R�̗Z��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�B ��s�̃v���p�[�Z��
�ȒP�ɂ���3�̗Z���ɂ��Ă������������܂��B
�u���{������Z���Ɂv�͈ȑO�A�u�����������������Z���Ɂv�ƌ���ꂽ��s�ŁA��ɏ��K�͂ȉ�Ђɑ��ėZ�����鐭�{�n�̋��Z�@�ւł��B
����20�N10���Ɂu�����������Z���Ɂv�@�u�_�ы��Ƌ��Z���Ɂv�@�u������Ƌ��Z���Ɂv�@�u���ۋ��͋�s�v�@��4���������A�u������Г��{������Z���Ɂv�i�ȉ��A������Ɂj���a�����܂����B
������ЂɂȂ�܂������A�����͐��{���S�z��ۗL���邱�Ƃ��@���Œ�߂��Ă���A�]���܂łƓ��l�ɐ��{�n���Z�@�ւƂ��ĉ^�c����Ă��܂��B
���{�̐�������̂��߂ɁA���Ԃ̋��Z�@�ւ�⊮����̂��{���̖ړI�ł��邽�߁A������Ƃ⎩�c�Ǝ҂ɑ��Ė��Ԃ̋�s���ϋɓI�ȗZ���������s���Ă���܂��B
����͐�����ɂ����{�n���Z�Ƃ��ĉc���Nj�����̖ړI�Ƃ��Ă��Ȃ�����ł��B�܂��A�J�Ǝ����ɂ��Ă��n�Ǝ������r�I�ϋɓI�ɗZ�����s���A�x�����Ă��܂��B
����́A�M�p�ۏ؋���Ƃ������I�ȋ@�ւ��ۏؐl�ɂȂ��Ă���Ė��Ԃ̋��Z�@�ւ���Z�����鐧�x�̂��Ƃł��B�ۏ؋�����g���Z���̂��Ƃ��u�v���p�[�Z���v�ɑ��āu���x�Z���v�Ƃ����܂��B
��s��M�p���ɂȂǖ��Ԃ̋��Z�@�ւ���Z���ɂ��āA�M�p�ۏ؋���̕ۏ��邱�ƂŁA�ʏ�ł͖��Ԃ̋�s����Z�����ɂ����������Ƃł��Z�����邱�Ƃ��ł��܂��B
���̏ꍇ�A�����̂ق��ɕۏؗ����x�����K�v������܂��B
�M�p�ۏ؋���̕ۏ��邱�ƂȂ��A��s��M�p���ɂȂǂ̖��Ԃ̋��Z�@�ւ���Z�����邱�Ƃ������܂��B����́A��s��100���̐ӔC�������Ă�����݂��Ă���邱�Ƃł��B��
�܂�A������Z�����ł��t�����ꍇ�A��s��100���̑�������Ƃ������Ƃł��B���̂��ߒʏ�́A���S�ۂł͗Z�����Ă��炦�܂���B�܂��A������x�̎���(2�����̌��Z��)���K�v�ƂȂ�܂��B
�n�ƗZ��
�n�Ƃ����Ẳ�Ђ�l�͗Z�������Ȃ�!?�ʏ�ł���A�n�Ƃ����Ẳ�Ђ�l�͗Z�������܂���B
���łɑn�Ƃ��I���Č��Z��(���x�\)�������Ђł���A�Z���z�{�����i�ׂ��j��������Ԃɉ���ł��邩�ǂ����̔��f�ŁA�����݂������s����̗Z�����ȒP�Ɏ��܂��B
�������A�n�ƑO��n�ƊԂ��Ȃ����͌��Z��(���x�\)���Ȃ����߁A��s�����f���ł��܂���B
�������A��s�̑�D���ȃf�[�^�ɂ��ƁA�n�Ƃ�������Ђ�10�N��܂ő������Ă��������́A�Ȃ�Ƃ�������10���������ł��B�ԍϊ��Ԃ̓r���ʼn�Ђ������Ȃ��s�͑呹�ł��B
�Ⴆ�A�ǂ�ȑf���炵���r�W�l�X���f���������Ă����Ƃ��Ă��A���ɋ�s���Z�����������Ă��������Z��������\���[���ɓ������ł��傤�B
 ����̂� �u���v �ł��I
����̂� �u���v �ł��I�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
���ꂩ��n�ƁA��ƁA�J�Ƃ���l��n�ƊԂ��Ȃ��o�c�҂ɂ�������₷�����邽�߂ɍ����݂����Z�����x���ꂪ�u�n�ƗZ���v�ł��B
�n�ƊԂ��Ȃ��o�c�҂̂��߂ɐ݂���ꂽ�Z�����x�ł��B�ʏ�̗Z�����x�́A��Ђ̐M�p��(���т┄��Ȃ�)��R�����ėZ���̉ۂ����܂�܂��B�������A�n�ƊԂ��Ȃ���Ђ�l���Ǝ�͐M�p�͂��Ȃ����ŃX�^�[�g���܂��B
�{���ł���A��Ђ̐M�p�͂�R�����ėZ���̉ۂ���������Z�@�ւ��A�n�Ƃ����Ẳ�Ђ�l���Ǝ�ɂ��Ă̐R�����ł��܂���B�����ō����͂��߂Ƃ��������̂Ȃǂ��n�ƎҌ����̗Z�����x��������̂ł��B
��ʓI�ɑn�ƗZ���Ƃ́A���L�̂Q�̂��Ă���܂��B
�@ ���{������Z���ɂ��s���Ă���u�V�n�ƗZ�����x�v
�A �s�撬���Ƃ����������́A��s�A�M�p�ۏ؋�����͂��čs���Ă���u���x�Z���v
�ǂ���̗Z�������ʂ���_�Ƃ��āA�n�ƗZ���́A��葤�ɂƂ��Ĕ��ɗL���ȏ����ł�������邱�Ƃ��ł��܂��B�����͒Ⴍ�A��Ƃ̎��Ԃ͕s�v�A�ۏؐl�E�S�ۂ�����܂���B���̂悤�ȏ����ł�������邱�Ƃ��ł���̂́A�N�Ǝ������̓��T�Ƃ��l�����������B
�g����I���I�Z��
|
�ΏۂƂȂ�l |
|
|
���߂������ |
|
|
���Ȏ����̗v�� |
���ƊJ�n�O�A�܂��͎��ƊJ�n��ŐŖ��\�����I���Ă��Ȃ��ꍇ�́A�n�Ǝ�����3����1�ȏ�̎��Ȏ��������邱�Ƃ��m�F�ł�����B |
|
�Z�����x�z |
���Ǝ����܂��͐ݔ������p�r�͈̔͂ŁA1000���~�B |
|
�S�ہE�ۏؐl |
�s�v�ł��B |
|
�ΏۂƂȂ�l |
|
|
�Z�����x�z |
|
|
�S�ہE�ۏؐl |
�����k�B�V�n�ƗZ�����x�Ƃ̑g�ݍ��킹�ŕs�v�Ƃ��邱�Ƃ��ł��܂��B |
|
�ΏۂƂȂ�l |
|
|
�Z�����x�z |
|
|
�S�ہE�ۏؐl |
�����k�B�V�n�ƗZ�����x�Ƃ̑g�ݍ��킹�ŕs�v�Ƃ��邱�Ƃ��ł��܂��B |
�H�i�����Ƃ̕��̎�������X�܊J�ݎ����A���H�X�◝���e�ƕ��̐ݔ������AIT�������s���Ɩ����P��o�c�v�V���s�����̃R���s���[�^�w�������A�V����1�l�ȏ�̌ٗp���s�����̉^�]�����ɑ���Z�����x������܂��B�i����������{������Z���Ɂj
�n�Ƃ������͑n�Ƃ��Ă���5�N�ȓ��̖@�l�E�l�̕��̉^�]�E�ݔ������ɑ���Z�����x�B
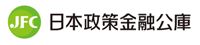 �@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@